TEPPENのプレイングで知っておくべきことをまとめていく所存でございます。

私は難しいことわからないので、なるべく簡単に書いていきます。
負けてしまう原因を考える

まずは、負けてしまう要因を考えます。
私がTEPPENで勝てない理由
- 相手のデッキがどう動くのか予測できない
- デッキに必須カードが入っていない、足りていない
- 環境(みんなが使っているデッキ)を把握できていない
- 焦ってしまう、出したいと思っても間に合わない
- 後先考えずにカードを出してしまう
- コストが足りずにカードが出せない場面がある
- 火力で押し切られる
勝てない理由は、もちろん、人それぞれ。単純にデッキ構築が甘いという可能性もありますが、カードゲームなので得意な展開はあるはず。

課金すればツエーってゲームではなさそうだね。最強リセマラカード積んでもすぐに負けちゃうんだけど。

強いカードは揃っているのに、他の人は勝てているデッキなのに。。。負けてしまう場合は、TEPPENのルールをうまく利用できていないのかも。
まずは、ざっくり以下の3点だけ振り返りましょう。思い当たる部分があれば、まずはそこだけ改善すればよろし。
改善策は全部やろうとしない
改善のポイントは「1つずつ」やること。ブログ運営にも言えることですが、やる施策は一つずつ。一気に全部に着手すると「どれが効果的」で「どれが悪さしている」のかが分かりづらくなります。焦らず一つずつ着手することが大事です。
TEPPENで勝つための対策案
- プレイングを見直す
- デッキを見直す
- ヒーローアーツを見直す
ではでは、1つずつ打開策を見ていきましょう。
TEPPENで勝つ「プレイング」を学ぶ
まずは、根本的な「ルール」を把握できていない可能性があります。プレイング面ですぐに改善できる施策をご紹介します。
アクティブレスポンスを活用する

まず、アクティブレスポンスについての理解を深めましょう。
アクティブレスポンスとは
アクションカードを使用すると、アクティブレスポンスなる横文字タイムが発動します。
アクティブレスポンスの特徴
- アクティブレスポンス中は、プレイが止まる
- レスポンスを受けるプレイヤーには10秒の待ち時間を与えられる
- アクティブレスポンス中は順番にアクションカードが使用できる
- ボーナスMPが2点加算される
- レスポンスにレスポンスで答える自分にもボーナスMPが発生している
2~3回プレイした方は「知っとるわ」という感じだと思います、回りくどい書き方してごめん。

でも、「アドバンテージをとる」ということに意識を向けるかで。「レスポンスに答えるかどうか」が変わってきます。
アドバンテージの取れるレスポンス対応
まず、アクティブカードを使用する側。使用者は「自分のタイミングでカードを使用できる」ので、基本的にはお得な行動です。ただ、確実に損する場面は以下。
- 自分がアクティブカードを使う
- 相手がレスポンスに答える(相手は2MP得)
- 自分がレスポンスに答えない(2MP損)
なので、カードを仕掛ける側は、「相手がレスポンスしてくる」ことを想定して、もう一枚アクティブカードが使えるようにしておくことがポイントです。
自分がレスポンスに応える場面が難解

じゃあ、基本的にアクティブレスポンスでアクティブカードぶっ放す習慣さえあれば勝てる? 簡単じゃん!
と、うまくいかないのがTEPPENが遠い理由です。
まず、レスポンスは「返さない方が得」する場合もあります。
レスポンスを返さない方が得する場面
- 相手にアクティブカードを多用させたくない時
- 相手のMPが余っている時
- 相手の手がすでに詰まっている時
- 相手が展開している時
かなりぼやっとしていますが、相手が「アクティブカード運用が主体」の場合は、レスポンスを返すことで、相手も「MP2得」することになり、展開が加速してしまいます。持ち札の回転も良くなってしまい、相手の選択肢が広がります。

逆に、相手がユニット強化に乗り出して、かつそのユニットを除去する手札があればあえて相手にアクティブカードを使わせてから除去、なんて感じで状況に合わせてレスポンスの対応も異なってきます。
アクティブカードは低コストから使う

私はうっかりやらかしがちですが、1MPのアクティブカードと、2MPのアクティブカードなら、1MPのカードから使うのが鉄則です。
低コストから順に使うメリット
- レスポンス発生でボーナス2MPを余すことなく使うことができる
- 残りMPが多く残せるため、対応の幅が広がる
とはいえ、チェイン次第ではレスポンス後に発揮した方が効果的なカードもあるので、この辺りは状況次第、ともいえます。
チェインでミスらない
補足しておくと、カードの効果が処理される順番によって「めちゃくちゃ得する」場面や「相手の行動を無駄死にさせる」技などがあります。
「後に使ったカードが先に処理される」ことを理解した上で、効果を上書きします。
効果処理順で得する場面
- ダメージ系にはシールドを重ねる
- 除去カードには発動条件を与えない
- 不利な効果をつけられるユニットをコストにする
破壊系のカードは「抹殺」以外は何かしらの代償を支払う必要があります。

むしろ、なぜ抹殺は無傷で相手のカードを倒せるのか。。。

MP6コストで黒単色デッキでしか使えないし、6コス消費後は大概しばらく動けないからね
以下のリストに「破壊カード」を載せておきましたが、条件を把握しておくと破壊を回避できたり、相手に予想以上のダメージコストを背負わせることができます。
除去・破壊カードの特徴一覧
- 実験記録の収集(味方ユニットを破壊、正面ユニット限定)
- 自業自得(味方ユニット破壊、相手はランダム)
- サンプル収集(ランダムな味方ユニットと敵ユニット破壊)
- 破壊の本能(対象ユニットの攻撃力分、ライフ犠牲)
- 無音の処刑(攻撃力2以下、ライフ半分以下で3以下限定)
- 殺戮の棘(3ライフ犠牲、攻撃力2以下限定)
- 漂う瘴気(2ライフ犠牲、MP3以下限定)

少し長くなってしまいましたが、アクティブレスポンスの使い方がTEPPENの鍵、と言っても過言ではありません。
コストの使い方を知る
アクティブレスポンスで、コスト節約できることを(身を以て)知ったところで、今度は「正しいコストの使い方」についてレクチャーを受けていきます。

わたくしめのお勉強に、皆さんもお付き合いください。
常にMPは対応できるようにためておく
よほど速攻決めなきゃいけない場面以外は、MPは残しておくのが鉄則です。攻撃を受けそうになるとついついカードを切ってしまいがちですが、手元にMPを2~3は残しておく習慣をつけるだけで、対応の幅が段違いです。手元にある除去札・妨害カードが使えるMPはキープしておきましょう。
ユニットの取捨選択が重要
これは、ユニットの出し方の問題です。
コストを節約する上では、手札にあるユニットをどのような優先順位で展開していくかが重要だと考えています。
最小コストでユニット処理ができればアドバンテージをとっていくことができます。相手のデッキの特徴をつかんだ上で、どのタイミングで主戦力ユニットを出すか、それまでのつなぎをどうするか、を考えて場に出していきます。
相手の残りMPを意識する

自分のプレイに集中しすぎずに、相手の残りMPについても着目しましょう
アクティブレスポンス中はMPが確認できる

普段は、相手のMPを見ることができません。(これは常時見えるようになっても良さそうですが、あまり負荷がかかると遅延の原因にもなるのでやむなしか)

ですが、アクティブレスポンス中に関しては、相手のMPを確認することができます!
残MPがあれば、「速攻をかけるタイミング」や「自分があとどれくらいコストを貯める余裕があるか」がわかるようになるので、レスポンス中は相手のMPチェックも怠らないように。
カードの配置を工夫する

地味な項目ですが、カードの配置、整理整頓できてますか?
カード位置の入れ替え、整理整頓できる
手札の配置順は随時変えることができる、ということを知らない方もきっといるはず。入れ替え、できます。
ユニットカードは左、アクションカードは右
一瞬のひらめきが大事なので、コンマ秒で配置できるように、ユニットは左側に寄せておくといいですね。また、アクションカードなどもある程度自分の中で配置の法則を決めておくと、似たような効果を持つ同コストのカードを間違えて使うミスを予防することができます。
使用するカードはドラッグキープ
リアルタイムバトル、ということもあって、相手の反射神経を超える速度でプレイすれば、相手が反応できずにユニットを配置することができます。

ネット環境や端末次第でラグが発生するのがつらいところだけどね
なので、基本的にはユニットカードはいつでも置けるように構えておくと相手の攻めに速攻で対応することができます。
ヒーローアーツも同様
私は「黒き選別」のウェスカーを使っているのですが、ヒーローアーツも構えておくと「相手の受けユニット」を攻撃直前に配置されても対応できることがあります。

相手はユニットをここにおくだろう、という時には、ヒーローアーツも相手陣地上で構えておくことをお勧めします。
相手のプレイを予測する
あー記事長くなってきたわぁ、だるいわぁ、でももう少しなのでお付き合いを。今度は、自分だけではなく、相手のプレイを予測し、妨害し、うざがられる術をレクチャーされます。
デッキの勉強をしておく
自分のデッキの使い方は色々調べますが、相手のデッキは調べませんよね。

相手が何を出してくるかなんてわからないもん。

とはいえ、環境デッキは概ね決まってきているので、「相手の動き」を知るためにはデッキ研究は必須です。
特にTEPPENでは考えている時間が少なく、相手のカードの効果を確認する余裕はありません。デッキの流れやよく使われるカードについては、動き方を確認しておきましょう。
初手で動くかどうかを見極める
混色デッキは最大MPが5です。これは、デッキ構築上の障害になるのはもちろんのこと、プレイの上でも大きな制約となります。

MPを損しないように、常に動いていないといけないからね。
デッキを見直してアド損を減らす
本当は、順序的にはヒーローアーツとデッキ構成を見直してから、プレイングを磨くべきなんですけども。デッキ構築の知識的な部分は環境に大きく左右されるのと、「大体の有用デッキはネットに落ちている」ので、記事作成の優先順位は低いのです。
バランスよく構築する
デッキ構築を見直す場合には基本的な要素があります。
- 初期手札に来て欲しいものかどうか
- 環境デッキとの相性
- プレイの妨げになっているカードはないか
- 火力不足じゃないか
- 目標とする勝率はどこか
全ての相手に勝てるデッキは存在しません。まずは、6割は勝てるデッキを作っていきましょう。そのためには、ランクマッチなどの環境を理解し、勝率を設定して統計をとっていくのが一番です。

普通にプレイする分には、統計というよりは体感で「負けが込んできたな」「このデッキ多いな」くらいが見直すポイントだと思います。
ユニットとアクションの割合
TEPPENはテンポの速いカードゲームなので、手札の回転率は高いと考えています。大事なのは初手の手札くらいで、あとはプレイングでケアできる場面がほとんどです。手札がユニットやアクションで固まってしまって身動きが取れない場合は、ユニットカードとアクションカードのバランスを見直す必要があります。

ユニットよりはアクションカードが多めの方が(アクションカードは回転がより速いので)動きやすいですが、デッキの特性によって比重は変わってきます。
TEPPENとマリガン
少し余談ですが、カードゲームで最初の手札を引き直すことを「マリガン」と言います。元々はゴルフの打ちなおしのことを言うようです。
カードの投入枚数を検討する
「初期手札に何が欲しいか」「バトル中に何回使用したいか」で、投入枚数も決まってきます。簡単なデッキの見直しの際には、投入枚数を微調整することから始めます。
コストのバランス
コストのバランスに正解はありませんが、勝てない要因に「思ったようにカードが出せない」「相手に先行されてそのまま負けてしまう」ということがあれば、コストの思いカードを起用しすぎている可能性があります。
高レアを詰め込む必要はない
これは単純に自分への戒めですが、高レアはゲットすると嬉しくて、ついつい詰め込みがち。
レアリティはあくまでもレアリティ。デッキによっては必須級の性能なので集金用に設定されているカードであって、万能というわけではないカードも多いです。レアリティよりはデッキとの相性でカードを選択しましょう。
ヒーローアーツを見直す
これは根本的な改善となります。デッキ構築から見直すことになるので。ただ、環境にはどうしても流行り廃りがあるので、合わせて戦いやすいデッキ、ヒーローアーツを見直していく必要があります。
各キャラのヒーローアーツを確認する
なんだか、記事を書いているうちに、環境は「リオレウスの逆鱗」と「モリガン」に変わったようですね。新弾投与も間近なので楽しみです。
リュウ
リュウのヒーローアーツとデッキ構築はこちらの記事をご確認ください。

リオレウス
リオレウスのヒーローアーツとデッキ構築はこちらの記事をご確認ください。
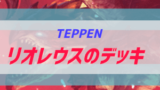
ジル・バレンタイン
ジル・バレンタインのヒーローアーツとデッキ構築はこちらの記事をご確認ください。

春麗
春麗のヒーローアーツとデッキ構築はこちらの記事をご確認ください。

エックス
エックスのヒーローアーツとデッキ構築はこちらの記事をご確認ください。
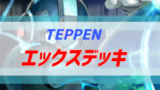
ダンテ
ダンテのヒーローアーツとデッキ構築はこちらの記事をご確認ください。

モリガン
モリガンのヒーローアーツとデッキ構築はこちらの記事をご確認ください。

アルバート・ウェスカー
ウェスカーのヒーローアーツとデッキ構築はこちらの記事をご確認ください。

ネルギガンテ
ネルギガンテのヒーローアーツとデッキ構築はこちらの記事をご確認ください。







コメント
「ゲーム アクション 破壊」に関する最新情報です。
ゲーム『ANTONBLAST』が12月4日にPC向けに発売され、リリース当日に「非常に好評」と評価されるなど、人気を集めています。この2Dアクションゲームは、『ワリオランド』シリーズから影響を受けており、主人公のDynamite Antonが盗まれた宝を取り戻すために立ち上がるストーリーが展開されます。ゲームの魅力は、作り込まれたステージやノリノリのBGM、破壊的なゲームプレイにあります。また、同じく『ワリオランド』に影響を受けた人気作『Pizza Tower』との類似性が指摘されており、両者の開発元は友好関係にあることも特徴です。今後、両作品のコラボレーションの可能性も期待されています。
https://automaton-media.com/articles/newsjp/antonblast-20241204-320479/
「パズル 99万9999 整頓」に関する最新情報です。
整理整頓パズルゲーム『A Little to the Left』が売り上げ99万9999本に到達し、高い評価を獲得しました。発売から約1年でこの大台を達成しました。このゲームはパブリッシャーのSecret Modeによって開発され、Nintendo SwitchやPCのSteamで発売されています。また、このゲームは日本語にも対応しています。
https://automaton-media.com/articles/newsjp/20231118-272680/